木村傘休
鈴木真砂女
1906年、千葉県鴨川に生まれる。
姉が 「俳諧雑誌」に投句していたのを機に句作に入り、大場白水郎に師事、「春蘭」に拠る。1947年から春燈に所属、万太郎の薫陶を受ける。
1955年処女句集『生簀籠』上梓。
1976年刊行の『夕蛍』で第16回俳人協会賞を受賞する。
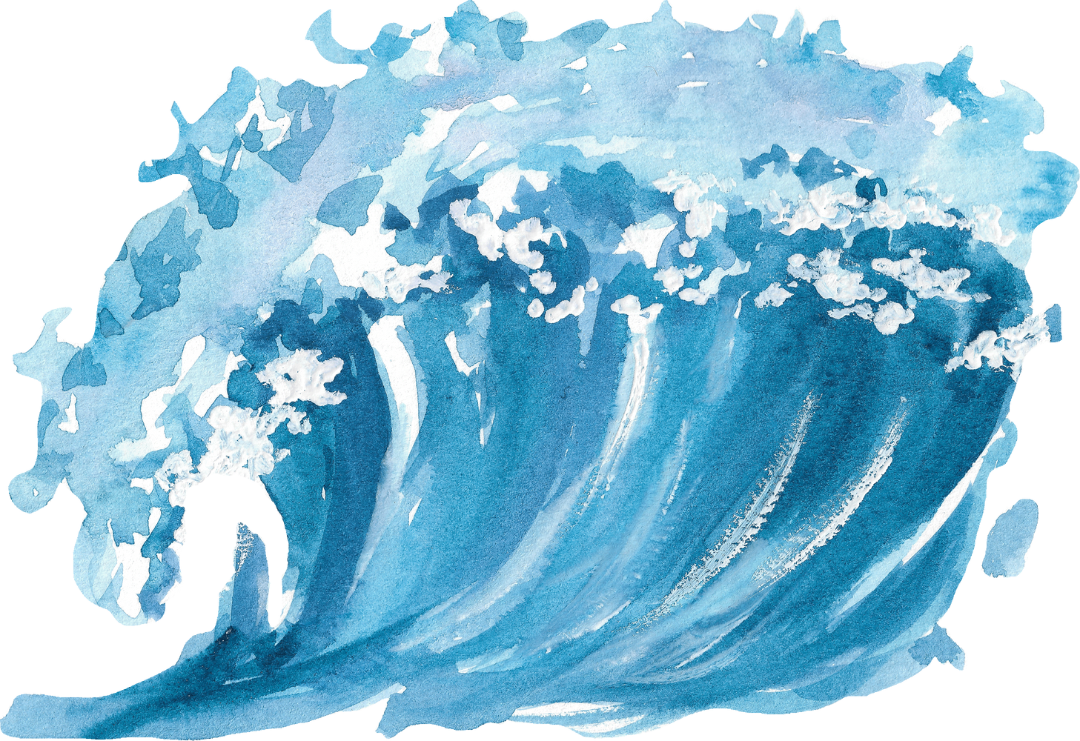
今月の句
No.6
亀鳴くやひとりとなれば意地も抜け
真砂女の運命は急転した。昭和30年4月15日、第一句集の『生簀籠』を上梓し、この受け取りに上京中、吉田屋旅館が全焼、泊り客の一人が焼死する大惨事が起きた。幸い隣家への延焼も、道一つ隔てた家族の住居も類焼を免れた。真砂女は自註で「火災の夜皆疲れて眠っている。私は眠れず、ひとり起き出したときこの句が出来た。心の余裕を見出して嬉しかった。この時再建出来ると確信した」とある。「亀鳴くや」の季語に49歳の真砂女の胆も太さが見える。波乱の人生はさらに続く。
これまでの鑑賞句
久保田万太郎の選を経て「春燈」創刊号(昭和21年1月刊)に載った作品。万太郎は詩人、俳人である夕爾句の詩韻の高さをいち早く見抜いた。夕爾の家は広島県深安郡御幸村(現・福山市御幸町)にあり、瀬戸内海から内陸に少し引っ込んでいる。港のある福山か尾道へゆく途次であろうか、遠くから雷のように海鳴りが聞こえてきた。海岸で大波が崩れる音が夕爾の胸を打つ。鬱々とした海鳴りを背景に銀色に輝く芒を手折る夕爾のダンディズムが見えてくる。夕爾三十歳の作。この年に妻・都を娶った.
三月の晴れた空に一朶の白い雲が浮かんでいる。真砂女はその雲が自分自身であるかのように思った。長姉柳(りゅう)の俳句の師匠であった大場白水郎の勧めで昭和11年より「春蘭」の会員となった。春燈へは昭和22年秋に入会。道ならぬ恋、生家の全焼、再建、離婚、そして離郷。無一文の51歳で銀座に小料理屋「卯波」開業。8年余りで借金を完済し、漸くにして芽木の空に浮かぶ安堵の雲を
見た。12年後富士霊園に建てた自身の墓碑に掲句を刻した。この句集「夕蛍」で第16回俳人協会賞を受賞。
生家の「吉田屋」旅館は昭和40年に閉館して売却され、1キロほど離れた海岸沿いに新しく「鴨川グランドホテル」として建設。代々の墓所は生家近くの浄土真宗福田寺の山腹にあるが、彼岸に両親や姉の墓参に帰郷した真砂女は、久しぶりに隣町天津の誕生寺を訪れたのだろう。境内の古松の大木に吹き寄せる浦風はまだ寒かった。その松風を仰ぎながら詫びる思いで亡き人々を懐旧した。
真砂女九十歳。近くを黒潮が流れる安房は温暖な気候から路地ものの花卉栽培が盛んで、菜の花畑も多く点在している。ホテルから太平洋を望むと、福山の詩人木下夕爾の<家々や菜の花いろの燈をともし>の句が思われた。この句集『紫木蓮』で第33会「蛇笏賞」を受賞。
自註によると、「洗足の大場白水郎邸でお花見句会が開かれ、たまたま上京中のこととえ出席。最高点をとった」とある。真砂女は「春燈」に所属した後も、最初の師白水郎の句会へは参加していた。白水郎は宮田製作所の重鎮で万太郎とは府立三中(現都立両国高校)、慶應義塾で俳句を通じて生涯の朋友であった。ところでこの句は、花見疲れで帰宅しそのまま座り込んで帯を解いたとある。とすれば大場邸で偶々出来た句ではなく、自信作として持参した句であろう。昭和25年の「春燈」12月号の『座談会「春燈」この一年を顧みる』で、高橋鏡太郎は「情感のこもった句が印象に残っている」と絶賛した。
真砂女の運命は急転した。昭和30年4月15日、第一句集の『生簀籠』を上梓し、この受け取りに上京中、吉田屋旅館が全焼、泊り客の一人が焼死する大惨事が起きた。幸い隣家への延焼も、道一つ隔てた家族の住居も類焼を免れた。真砂女は自註で「火災の夜皆疲れて眠っている。私は眠れず、ひとり起き出したときこの句が出来た。心の余裕を見出して嬉しかった。この時再建できると確信した」とある。「亀鳴くや」の季語に49歳の真砂女の胆の太さが窺える。波乱の人生はさらに続く。
吉田屋全焼から一年後、真砂女の奮闘で吉田屋を再建。以前にも増して商売は繁盛した。しかし翌32年1月10日、娘可久子の出ている芝居見物で上京中、姉の家に呼び出されて「身一つで家を出るか、主人の看病をするか」の選択を迫られ、無一文で家を去り、文学座の娘の寮に同居する。幸い女将としての真砂女の資質を知る4人の理解者から200万円借り受け、二か月後の3月30日に銀座一丁目の幸稲荷の路地に小料理屋「卯波」を開店する。51歳にして新たな人生が始まった。白い割烹着は自由に生きる道を選んだ証としての大好きな仕事着なのだ。
