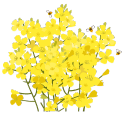福井拓也
久保田万太郎
1889年東京浅草生れ。俳人、小説家、劇作家。
1938年岸田國士、岩田豊雄らと劇団文学座を結成。
1946年1月から1963年5月まで『春燈』主宰。「家常生活に根ざした抒情的な即興詩」を唱導。1963年5月6日逝去。
1942年第4回菊池寛賞。
1947年芸術院会員。
1957年日本文化勲章、第8回読売文学賞。
句集『道芝』(1927年)、『ゆきげがは』(1936年)、『春燈抄』(1947年)、『流寓抄』(1958年)ほか。

今月の句
No.6
神田川祭りの中をながれけり
万太郎は「表面、どこまでも単純にみえる・・・・・・あくまでさりげなくとりなす」必要を説いた。その好例である。
まず「神田川」という固有名詞が地図的な、川を上空から見下ろす視点に読者を導く。その印象を「祭りの中」ががらりと変える。まさに今、祭りの華やぎに身を置く感覚、その中をぶらつく視点が入り込んでくる。そして「ながれけり」が二つを柔らかに縫い合わす。ここに俯瞰する視点と現場の視点とが一緒くたにされた、思えば不思議な情景が、何の不思議さもなしに生み出されるのだ。
これまでの鑑賞句
西脇順三郎はポエジー(詩情)の本質を、人間が生きる有限の世界と、無限の世界との連結が生み出す「はかなさ」に確認した。これは俳句を理解する鍵でもある。
たとえば掲句。新たに奉公人が姿を現すのは何も今年だけではない。昨年の春も、また来年の春もそうだろう。しかし「新參」の彼—今まさに「あかあか」と照らし出される落ち着かなさを感じている彼にとっては、一度きりのことだ。めぐりゆく季節のなかでただ一度の生を歩むこと。その不思議さが俳句を織りなしている。
次々と名詞を並べて一句を構成するのは、万太郎が好んだスタイルの一つ。ほかにも<短日や小ゆすりかたりぶッたくり>。<ばか、はしら、かき、はまぐりや春の雪>となるとどこか風情があるが、「忍」の句には〝雅〟と〝俗〟の取合せが醸し出す諧謔が色濃い(鈴木直充)。〝こんなものでも俳句になります〟と、したり顔が目に浮かぶ。
「〝余情〟なくして俳句は存在しない」と万太郎は述べたが、これに囚われすぎてもいけないようだ。読み手の心に染み入るばかりが俳句ではないのである。
「ボタン一つのかけちがへ」。万太郎にとってそれは取返しのつかないものである。曰く「かけちがえると、そのあとが、ずっと、いけない」。その哀しみを彼はひたすらに探索してきた。愛読者はたとえば戯曲「雨空」を思い浮かべるところだろう。
同じ比喩を「長崎BREEZE」という曲で用いたさだまさしも、やはり最後に気づくものとしている。いっそ気づかなければ幸いなのだろう。あまりにも茫漠とした「春の日」との取合せは、皮肉にして痛切である。
万太郎の句集『これやこの』の評を求められた石田波郷は、掲句に「ばつてんをつけた」。しかし後に評価を改める。「新しい俳句」を目指す「文学青年的な俳人」の「深刻調」とは違う、句のリズムの「たるみ」にこそ「万太郎の偉さ」があると気づかされたというのである。
これは万太郎の追悼座談会での発言で、実際は少し違っている。波郷は掲句に丸をつけ、「この「たるみ」は作者独特の味あり、「たるみ」は素人には向かぬ芸也」と付言していた。記憶違いもまた興味深い。
「わたしの大好きな明るい句」と記したのが春燈俳句会の先達、万太郎に直接指導を受けもした中村嵐風子(本名哮夫)。『ラ・マンチャの男』の演出家として高名な彼は、掲句をチェーホフの戯曲『ワーニャ伯父さん』に重ねている。曰く「ほっと息をついた人間の平和な一瞬が、見事にストップモーションの形でとらえられている」。
連用中止法と読点の反復は散文的だが、「さてそこで」と急に口を噤む。この「ストップモーション」がいかにも俳句らしい突き放し方で、見事なバランス。
万太郎は「表面、どこまでも単純にみえる・・・・・・あくまでさりげなくとりなす」必要を説いた。その好例である。
まず「神田川」という固有名詞が地図的な、川を上空から見下ろす視点に読者を導く。その印象を「祭りの中」ががらりと変える。まさに今、祭りの華やぎに身を置く感覚、その中をぶらつく視点が入り込んでくる。そして「ながれけり」が二つを柔らかに縫い合わす。ここに俯瞰する視点と現場の視点とが一緒くたにされた、思えば不思議な情景が、何の不思議さもなしに生み出されるのだ。